第三回SPRING起業セミナー開催!Vol.1
昨年の10月18日(木曜日)に、第3回目となるSPRING起業セミナーを開催しました。
今回の記事でも、2回にわたり、1時間30分にわたる
濃密なお話の一部をご紹介いたします。(前編)
SPRING起業セミナーとは、川崎町でご活躍されている起業家の方々をお呼びし、
起業に至った経緯や自身のビジネスへの想い、今までの困難や乗り越え方に等について、
起業家の目線からお話いただく講義です。
第3回目となる今回のゲストは、川崎町にて伝統工法による家づくりや家具づくりをしている、
伊藤建築の伊藤達生さんにお越しいただきました。
伊藤さんや伊藤建築、伝統建築の魅力とともに、川崎町で起業することの魅力もお伝えしていきます!
なぜ大工になることを決めたのか
中学生の頃から、漠然と自分の好きなことをして生計を立てていくつもりだったという伊藤さん。
そのため、どのような職業に就いて暮らしていくか、という観点ではなく、
どんな仕事であれば生業として成立するか、という観点で、仕事を探していたそうです。
とは言いながらも、大学時代までは建築という道に歩むことも決まっていなかったとのこと。
そこで、自分の道を模索するため、半年ほど海外を放浪された中で、見えてきた軸が、
「日本人らしい仕事をする」かつ「世界中どこへ行ってもやっていけるもの」。

例えば、料理や建築は世界中のどこでも需要があり、一流の職人がいるような世界です。
小さい頃から手先が器用でモノづくりに親しんでいた伊藤さんは直感的に建築の道が性に合うと考え、
大工の道に進むことを決められました。
一口に大工といっても、そのキャリアには大きく3つの方向性が考えられた、という伊藤さん。
(1)一般の工務店に入り、一般的な木造住宅に携わる道
(2)(1)の中でも設計事務所の元請けとして、個性的な住宅を求める施主さんのこだわりを形にする道
(3)宮大工や数奇屋大工など、神社仏閣や茶室などに携わる道
25歳から「大工」を志した伊藤さんからは、一人立ちするまでに長年修行期間を求められる
宮大工や数奇屋大工になるのは年齢的な限界を感じていたそうです。
必然的に一般木造住宅を作る道を選び、工務店に所属し、大工見習いになられました。
多くの大工さんの中で何か特色を出していく必要があると考えられていた伊藤さんは、
何かヒントを得ようと、とある講習会に参加されました。
その講習会には、今日の伝統建築業界をリードする方々が多く参加されており、
そこで「伝統建築」の道に出会います。
大手工務店で、一般住宅を建てる大工を目指し続けても、一人の大工としても価値を発揮しにくいと判断した伊藤さんは、
日本で古くから受け継がれている伝統技術を身につけた一般家屋向け大工を目指すことにされたそうです。
伝統建築の道へ
伝統建築は、建造から既に数100年と経っても残り続けている古建築からもわかるように、
非常に丈夫で家が長持ちする建築技法です。
長い時間の流れを経ても老朽化せず残る家を建てることを考えると、
必然的に新しい技術ではなく、既に確立された伝統技術をいかに学ぶかが鍵になっていきます。
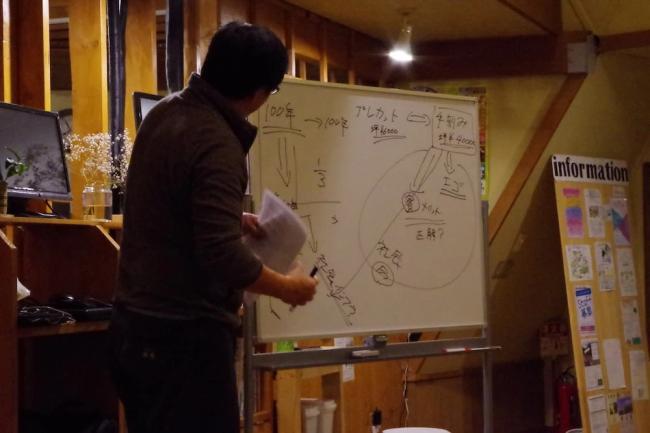
伝統技術を用いて家を建てようと思えば、必然的に無垢材を選ばなければならないそうです。
無垢材を扱うことは、よく用いられている集成材に比べ、容易なことではないそうです。
どう使えばその素材が生きるのか。木に習い、木に従うというスタンスが求められます。
伝統技術を身につけていく上で、ベースとなっていたのは、大工業界の狭い世界で完結させず、
それぞれの一流の職人から学ぶということ。
伊藤さんは、何事も飛び抜けた人に教わることが最も効率的に学ぶことができるとお話していました。
例えば、カンナ等の刃物の取り扱いや手入れに関することは刃物屋などにたずねていき、
一つ一つの技術を一流のプロから学んだそうです。
さて、Vol.1では伊藤さんが伝統建築にたどり着くまでの道のりをご紹介させていただきました。
次回は、伊藤さんの伝統建築にかける想いや、川崎町で起業したことの意義、今後の展望等についてご紹介いたします。
Vol.2もお楽しみに!